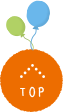保育園が実践する子どもの胃腸炎予防と対策、嘔吐処理の手順

子どもが胃腸炎にかかると家族は心配でなりませんよね。胃腸炎は家庭内で感染することも多く、感染が拡大することがあります。胃腸炎にかからないようにするためには、またかかってしまった時はどうすればいいのか?この記事では、HITOWAキッズライフの保育園で実践している胃腸炎の予防や対策をご紹介します。子どもを含め多くの人が集まる感染症リスクの高い保育園だからこそ行っている科学的根拠と専門的知識をもとにした予防と対策です。ご家庭の子育てにも生かせる予防方法や事前準備、感染後の対応手順についてご紹介いたします。胃腸炎を正しく理解することで、子どもや家族の健康を守ることができます。ぜひ、この記事を読んで、胃腸炎に負けない家庭を作りましょう。
胃腸炎ってなに?
胃腸炎とは、胃や腸に炎症が生じている状態のことで、その大半がウイルスや細菌が原因の感染性胃腸炎です。一般的に下痢や嘔吐などの症状が出ます。小児期の胃腸炎は主にウイルス性胃腸炎のため、細菌性胃腸炎についての説明は省かせていただきます。
ウイルス性胃腸炎について
「ノロウイルス」「ロタウイルス」などのウイルス感染によって引き起こされる胃腸炎で、毎年秋冬にかけて流行します。
一般的には罹患した人の便や嘔吐物にウイルスが含まれており、その処理の際に触れた手や指から、最終的に口に運ばれることで感染します。また、感染力の強いウイルスの場合は便や嘔吐物などの残留物が乾燥し空気中を浮遊、それを吸い込むことでも感染を起こすことがあります。
発熱を伴う嘔吐、半日以上水が飲めない、尿の量が少ない、便の色がいつもと違う(白っぽい・血が混じるなど)といった症状がある場合には、早めに医療機関での受診を検討しましょう。
子どもの胃腸炎、主な症状と看病の方法
症状は大人と同じく吐き気、嘔吐、下痢、発熱、腹痛などが主です。
特に乳幼児の場合は嘔吐による脱水を引き起こしやすいため注意が必要です。また、乳児ではけいれんを起こすこともあります。下痢・嘔吐をしている最中は、飲食をすることによって再び吐き気が出たり、嘔吐を誘発してしまうこともあります。ピーク時は、脱水にならないよう湯冷ましや麦茶など少量ずつこまめに水分補給をすることを優先します。食事を摂ることは控え、症状が落ち着いたら消化の良い食べ物(おかゆ・煮込みうどん・野菜スープなど)から始め、少量ずつ子どもの状態に合わせて食べさせていきましょう。
お腹を休めるために、この時期は乳製品、おかし、脂肪分・香辛料・食物繊維の多い食事は控えることをおすすめします。
嘔吐や下痢は、体の中に入ったウイルスや細菌などの病原体を体の外に排出する反応です。無理に止めずに、子どもの状態を見守りながら症状が治まるのを待ちましょう。
感染症予防の基本
胃腸炎に限らず、すべての感染症予防の基本は「手洗い」
HITOWAキッズライフの保育園では、「手洗い」の基本が身につくように子どもたちにも健康教育を行います。まだ幼い子どもたちですが、そこは保育士の腕の見せどころ。子どもがすすんでやりたくなる「手洗い」を伝えています。
【手洗い】
石けんやハンドソープを使い両手をこすり合わせるようにして洗い(こすり洗い)水で洗い流すことで、手に付いた汚れと一緒にウイルスは大幅に減少します。こすり洗いは30秒が目安です。大切なのは、指の間、指先、爪の間、手のしわ、親指の周り、手首をまんべんなくこすり洗いをして、しっかりと洗い流すことです。
感染症予防のための環境整備
保育園は子どもを含む多くの人が集まり集団生活する場所で、胃腸炎だけではなく様々な感染症が流行するリスクがあります。そのリスクを最小限に抑えるための感染症対策を日々実施しています。感染症対策の基本は、主な感染経路(接触・飛沫・空気)に対しての対策となります。特に子どもの感染症の原因となる感染経路は、「接触・飛沫」によるものが多いため、日常的に触れるものを清潔に保つ「日常の清掃」、次に「換気」の対策を優先しています。
【清掃】
保育園で働く保育士たちは、床の清掃、テーブルの清掃を行っています。感染症が流行した時はアルコールや次亜塩素酸ナトリウム溶液を使用し消毒液洗浄を行います。
HITOWAキッズライフの運営する保育園では、100以上の運営施設における事例や最新情報の共有と研修を実施し、より良い保健衛生・安全対策を講じています。
【換気】
水痘(水ぼうそう)に代表される「空気感染」や新型コロナウイルスのような「エアロゾル感染」など、空気を介して感染する病気の流行を防ぐためには「換気」も有効です。換気のポイントは風の通り道(入口と出口)を作ること。なるべく対角線上に2ヶ所以上の窓を開けると、風の通り道ができて効率よく換気ができます。また、窓は全開にするよりも少しだけ開けた方が空気の流れが速くなるので効率的です。
保育園での健康教育
「手洗い」は、お散歩の後、トイレの後、食事の前など、乳児の時から生活の中で繰り返し行うことで手洗いのタイミングを覚えていきます。
保育園での手洗いと手洗いタイミング
HITOWAキッズライフの保育園の子どもたちは、園到着時、お食事前後、おやつを食べる前後、トイレに行った後、お庭や公園で遊んだ後、粘土や絵の具、玩具で遊んだ後、動物を触った後、手が汚れてしまったときに、手洗いをしています。子どもが一人でできるようになるまでは、保育士がサポートします。
洗い残しのチェック
ササッと済ませがちな手洗いですが、洗う手順がわかる歌を歌うなど、子どもが手洗いを楽しいと思えるよう工夫し、洗い残しがないよう伝えています。また、小さな手指でも泡立つよう、泡タイプのハンドソープにすることで汚れやウイルスをより落としやすくします。

子どもが手洗いを終えたら、洗い残しがないかチェックしてみましょう。洗い残しやすいところを子どもと一緒に確認し、汚れを落とすことを意識して洗えるようにします。(※2)


手を洗う理由と正しい手洗いを楽しく伝える
幼児の手洗いの最初のステップは、「嫌がらない」ように楽しい雰囲気で手洗いを習慣化することです。子どもをうまくサポートしながら、大人も一緒に練習する気持ちで取り組みます。上手に手洗いができたら、ほめてあげましょう!また、病気や手洗いに関する絵本を一緒に読むことで、その必要性と正しい方法を学んでいきます。
子どもへの健康教育について
幼児クラス(3~5歳児)になると「どうして手を洗わなきゃいけないの?」「おなかが痛くなるってどういうこと?」と、子どもから自分の体で起きることや、素直な疑問をぶつけてきます。
そんな時は、身体の仕組み、どんな病気があるのか、病気になった人の気持ちに寄り添うことなどがテーマの絵本を、一緒に読むことでその必要性と正しい方法を伝えています。
HITOWAキッズライフの保育園は「絵本から広がる保育」を大事にしており、選書を強みとする絵本ナビと提携して子ども達が良質な絵本に出会える機会を増やしています。
子どもへの健康教育におすすめの絵本


- ゲーゲー ピーピー おなかのびょうき
細谷亮太 文
早川純子 絵
童心社 刊 - うんぴ・うんにょ・うんち・うんご ─うんこのえほん─
村上八千世 文
せべまさゆき 絵
ほるぷ出版 刊
子どもの嘔吐に備える・対応する
HITOWAキッズライフの保育園では、胃腸炎などで嘔吐した場合に嘔吐物を処理する備品を保育室に準備して汚染場所が最小限にすむような工夫もしています。処理手順をマニュアルにまとめ、保育園の誰もが対応できるよう研修も行っています。ご家庭内でも、家にあるもので嘔吐処理セットを準備しておくと、いざというときに手早く処理ができますので参考にしてみてください。
【事前準備】嘔吐処理セットを用意しておく


嘔吐処理セット内容(上記写真参照)
- バケツ(事前にゴミ袋を2枚ほどかけておくと良い)
- 消毒液(次亜塩素酸ナトリウム(台所用漂白剤を希釈したもの))
- 使い捨てのマスク、手袋2枚、エプロン
- ゴミ袋またはビニール袋 数枚
- トイレットペーパーやペーパータオル、新聞紙、古い布など
【事後処理】嘔吐処理の手順とポイント
- 嘔吐物をペーパータオルなどで覆う
- 吐いた場所を中心に半径2mくらいまで汚染が広がることを想定し、処理する人はマスク・手袋・使い捨てエプロン等を着用し、嘔吐物に触れないようにしながら外側から内側に向かってペーパータオルなどで嘔吐物を集めビニール袋に入れる
※手袋は2枚重ねて装着します。 - 嘔吐物を取り除き、汚染場所を次亜塩素酸ナトリウム(台所用漂白剤を希釈したもの)を0.1%に薄めた消毒液(※)を浸したペーパーで消毒し、10〜15分放置する
- 処理で使用した手袋・マスク・使い捨てエプロン等を、汚染した面を内側に返しビニール袋に入れ破棄する
- 処理が終了したら手洗いをし、部屋の換気をする
- 汚れた子どもの衣類は、家庭内で家族への感染防止のため手袋・マスク・使い捨てエプロン等を着用し嘔吐物を取り除いたのち、85℃以上の熱湯に1分以上つけて熱湯消毒する
※消毒用液の希釈方法:水 500mlに対して、台所用漂白剤(5%)を10ml(ペットボトルキャップ2杯分)
※衣類洗濯用洗剤(酸素系漂白剤)には、消毒効果はないため吐物・汚染物の処理には適しません。
子どもを胃腸炎から守るために
子どもも大人も、症状の自覚がなくてもウイルスを保持していることがあります。
大人から子どもへ病気が移ることを防ぐために、家族全員がしっかり手洗いをして、家庭内でウイルス感染を拡げないよう予防しましょう。
※本記事は2023年12月時点の情報をもとに作成しております。掲載情報については、追加や変更などの更新が行われる可能性があります。
HITOWAキッズライフのご案内
保育園の入園募集
HITOWAキッズライフの運営する保育施設では、見学・イベントを定期的に開催しています。首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)を中心に北海道・沖縄を含め108施設(児童発達支援事業所を除く)を運営しておりますので、お気軽にお申し込みください。
児童発達支援事業所の利用者募集
HITOWAキッズライフでは、首都圏(東京・千葉・埼玉)に4つの児童発達支援事業所「アイビーキッズ」を運営しており、子どもとその家族の心の基地になるような支援を行っております。見学や相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
保育士など保育園勤務スタッフ募集
HITOWAキッズライフでは保育士、栄養士、調理師、看護師、無資格でも勤務いただける保育補助や調理スタッフなどの人材を募集しております。新卒・中途「つながり保育」の理念のもと、スタッフにとっても働きやすい保育園運営を心がけております。